OUR HOSPITALITY(邦: 荒武者キートン)[1923]
- fdsmoviecircle
- 2018年5月7日
- 読了時間: 8分
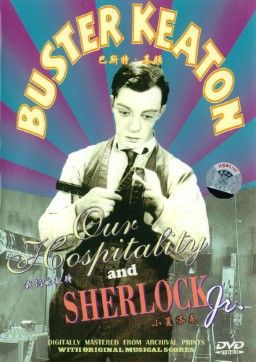
監督 バスター・キートン
ジョン・G・ブリストーン
脚本 ジャン・ハベッツ
クライド・ブラックマン
ジョセフ・ミッチェル
出演 バスター・キートン
ジョー・ロバーツ
ナタリー・タルマッジ
ジョセフ・キートン
ラルフ・ブッシュマン
撮影 ユージン・レスリー
ゴードン・ジェニングス
美術 フレッド・ガブリー
製作 ジョセフ・M・シェンク・プロダクションズ
配給 メトロ・ピクチャーズ・コーポレーション
キートン演じる青年のウィリー・マッケイは、地所の相続のために生まれ故郷の町へと汽車に乗って帰り、途中で美しい女性と出会い惹かれ合う。しかし、故郷の町についてみると、かつてマッケイ家と対立していたキャンフィールド家の男たちに命を狙われるハメに。しかも、汽車で出会った女性はキャンフィールド家の娘だった。

『荒武者キートン』は1923年の作品であり、最も素晴らしい喜劇俳優にして、映画監督でもあるバスター・キートン監督・主演の代表作のひとつでもあります。原題の「OUR HOSPITALITY」は、我々の心地よく素晴らしい接待という意味であり、作品を見てもらえれば分かることですが、かなり皮肉めいたタイトルでもあります。 アクション・シーンの独創性とダイナミックさは、他と比較できないほどの力強さを持っています。スタントマンを使わないで、自分でやってのける彼は全身ケガだらけ、骨折は日常茶飯事だったようです。 作品自体は監督の演出が冴え渡り、雨と影の使い方はその後に起こる不幸を暗示していて興味深く見ました。コミカルなシーンも次から次に現れ、そのどれもが観客を唸らせる工夫のある演出でいっぱいです。山・川・列車などあちこちに出没して観客の目を飽きさせず、テンポ良く作品を転がしていきます。特に興味深く見ていたのは列車での機知に富んだ演出であり、後々のストーリーに繋がってくる女性や犬との絡みもさりげなく挿入されています。列車というと速いイメージがこびれついていますが、ここで出てくる列車は馬車を繋いだような代物であり、牧歌的な印象がありました。アクションとコメディーの幸福な融合を見られる67分間です。 見れば解る、サイレント映画の魅力が全篇に貫かれています。時代を超えて、人種の、そして言語の壁を越えて理解できた「映画」(サイレント)こそ映画人が目指すべき映画の頂であるべきです。世界的なコミュニケーションを取れる作品を送り出すには、モンタージュを如何に極めるかが映画作家の腕とセンスの見せ所です。よくスピルバーグ監督を評して「大衆迎合で芸術性が無い」とかいう人を見かけますが、大間違いです。大衆に解る、というのが映画芸術の基本であるはずなのです。 無表情な顔、こういわれることの多いキートンですが、彼の目には哀しみを、彼のアクションからは彼の必死さと映画への情熱を見てとれます。彼の目から、そして身体全体を使ったアクションから、彼の感情と意志を探っていただきたい。
バスター・キートン(Buster Keaton)

カンザス州ピクアにて、父ジョー、母マイラとの間に生まれた。両親は舞台芸人で、キートンも子どもの頃から、子役として両親とともに各地でヴォードヴィルの巡業を続けた。初舞台は1899年、まだ4歳の頃だった。そして「キートン3人組 (The Three Keatons) 」として舞台に立ち、荒っぽいギャグを売り物にした。父親のジョーが、小さい彼の身体を逆さに持ち上げてぶんぶん振り回す「人間モップ」を泣き顔一つせず演じていたことは有名な話である。後に弟ハリー(愛称はジングルズ)と妹ルイーズも舞台に立ち、「5人組」としても人気を博した(後期はバスターと両親による「3人組」に戻った)。イギリスで公演するなど、海外巡業も経験した。キートンが映画界に進出する直前まで活動が続いたが、その時点で完全に解散している。
また、ジョーはかねてから映画という媒体を評価していなかったようだが、14本の映画に出演し、家族で共演する作品もいくつか存在する。『デブ君の勇士』 (A Country Hero) では息子バスターとの初共演を果たしているが、フィルムは現存していない。マイラ、ハリー、ルイーズにも映画出演経歴がある。家族全員が勢揃いした作品こそ存在しないが、『キートンの西部相撲』 (Palooka from Paducah) や『列車の愛の巣』 (Love Nest on Wheels) などでは家族との共演が確認できる。
1917年にニューヨークへ渡り、当時、マック・セネットのプロダクションで大人気だったロスコー・アーバックルの誘いを受けて映画界入りを果たした。映画初出演作品は『ファッティとキートンのおかしな肉屋』 (The Butcher Boy) であるが、キートンが新人ながら1度も撮り直しすることなく撮影を終えたという逸話が残っている(出演時間は決して短くない)。その後、アーバックル主演映画に立て続けに脇役として出演した。
1918年には第一次世界大戦による徴兵で、一時映画出演から離れた。その際、回復したものの耳を負傷している。
体を張りながらも、無表情で一途な役柄を特徴としたことから、「The Great Stone Face(偉大なる無表情)」というニックネームがつけられた。他にも当時から「すっぱい顔」「死人の無表情」「凍り付いた顔」「悲劇的なマスク」などと呼ばれた。アーバックル主演映画に出演していた頃は、このキャラクターは定まっておらず、笑顔や泣き顔、更には激怒した顔など、豊かな表情を見受けることができる。特に無表情が定着したのは独立後である。チャップリンの撮影施設を買い取り、キートン撮影所を設立した時期と重なる。
初単独監督作品は1920年に撮影された『キートンのハイ・サイン』 (The High Sign) であるが、キートン本人が気に入らず、公開が見送られた。同年、監督作品である『文化生活一週間(キートンのマイホーム)』(One Week) が公開されている。なお『ハイ・サイン』は、キートンが『キートンの電気館』 (The Electric House) の撮影中に足を骨折する怪我に見舞われ(エスカレーターに挿まれた)、撮影中止の事態に陥ってしまった際の埋め合わせとして公開された。『-電気館』は再度の撮影の後、1922年に公開されている。
1920年代を中心に大変な人気の映画俳優となった。1923年まで18本の短編を撮影した後、自らの撮影所でメトロ・ゴールドウィン・メイヤー(以下MGM)やユナイテッド・アーティスツ配給の長編作品の製作に着手した。長編第1作『キートンの恋愛三代記』 (The Three Ages) から長編第10作目である『キートンの蒸気船』 (Steamboat Bill Jr.) までの10本である。
1928年、キートンは自身の撮影所を手放し、MGMと契約した。当時、MGMは既に多くのスターを抱え込む大手映画製作会社だったが、キートンは次第にMGMでの映画製作システムに対応できなくなってしまう。後のキートンが自らの自伝でも、過ちとして語っているように、MGMでの時代は人生の転機を迎えた時期だといえる。それでも興行的には成功を収めている作品も存在し、特に1928年に公開された『キートンのカメラマン』 (The Cameraman) は、その年のMGM作品の中でも抜きん出る興行成績を記録した。
1933年までMGMで映画を撮り続けたが、徐々に仕事は衰退した。今日では衰退の原因が、サイレント映画の衰退と、代わりに台頭するようになったトーキー技術において、キートンのハスキーボイスがそれとマッチしないと評されるところが多い。初トーキー作品となったのは『キートンのエキストラ』 (Free and Easy) であるが、この作品においては、興行的に大成功を収めている。ヴォードヴィル時代に鍛え上げられたダンスと歌声を披露しているくらいである。朗々たる美声とはいいがたいが洒落た感じのよい歌声であり決して悪声ではない。 他にも、衰退の原因として考えられている点が、MGMの分業方式・或いはスター方式が手作り主義のキートンに合わず、さらに今まで一緒のチームのメンバーが解体してしまった事などが挙げられる。サイレント時代の傑作『キートン将軍』などのカメラワークはいま見ても目を見張るものがあるが、これらのスタッフは各スターの製作で文字通り引っ張りだこであって、複数の喜劇映画に名を連ねている。
MGM時代の後期はジミー・デュランテとのダブル主演という趣の作品に出演した。この頃から酒に溺れる日々が続き、撮影を丸1日潰してしまう出来事も起こった。また、MGMとの約束をキャンセルしてしまう出来事も重なり、これがきっかけとなり解雇を言い渡されてしまう。その後はメキシコ、イギリス、フランスで長編作品を製作したが、同時に酒量が増えアルコール使用障害に陥った。破産も経験している。これに前後して『荒武者キートン』で競演した妻との離婚、看護婦であった第2夫人との結婚・離婚などを経験し、「発狂」と新聞に報道されてしまう羽目にまで立ち至っている(これは日本の新聞にも写真つきで報道された。旧い映画評論などはいまだにそのまま書かれている)。
1930年代半ばには、エデュケーショナルで短編作品に出演(主演)するようになった。また、1940年代にはコロンビアやユニヴァーサルにも迎え入れられた(主に脇役)。他にも監督、原案の提供、ギャグの創作や指導などの仕事をこなしている。また、マルクス兄弟の作品に原案を提供したり、ギャグの指導を行っている(兄弟の反応は微妙なものだったという)。が、マルクス兄弟の特徴となる視覚的で不条理なギャグにはキートンの影響が随所に感じられる。しかしながら当時は既にハリウッドの一線から完全に退いていると考えられていた。
1950年代はTVショーの出演やヨーロッパでの舞台を続けるなど、仕事に恵まれた時期だった。映画でも1950年にはビリー・ワイルダー監督の『サンセット大通り』に出演。また1952年には『ライムライト』に出演、チャーリー・チャップリンと初共演を果たした。これらの仕事や、黄金時代のフィルムが倉庫から探し出されてリバイバル上映されるなど、キートンへの再評価が高まった時期である。1957年には伝記映画『バスター・キートン物語』も公開された。最晩年の出演作、『ローマで起こった奇妙な出来事』 では、セリフも少なく、ただそのへんを走っているだけのマラソンランナー役(最後の大どんでん返しの中心人物だが)だったが、それでもクレジットタイトルでは別格扱いだった。
1966年2月1日、肺癌によりカリフォルニア州ウッドランドヒルの自宅で死去。70歳。




コメント